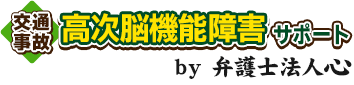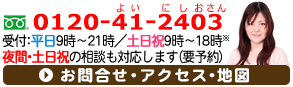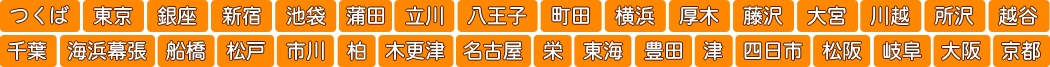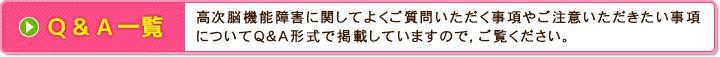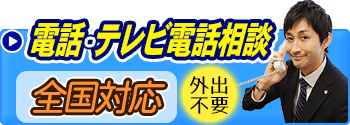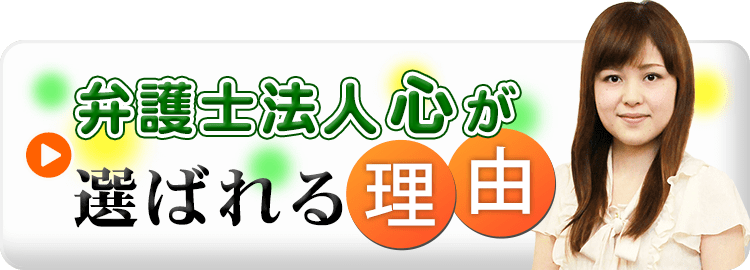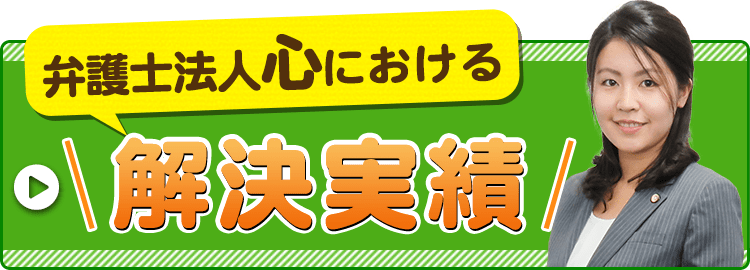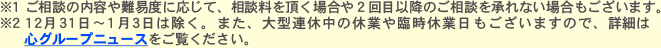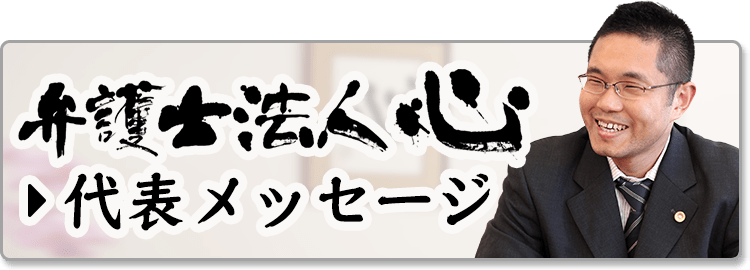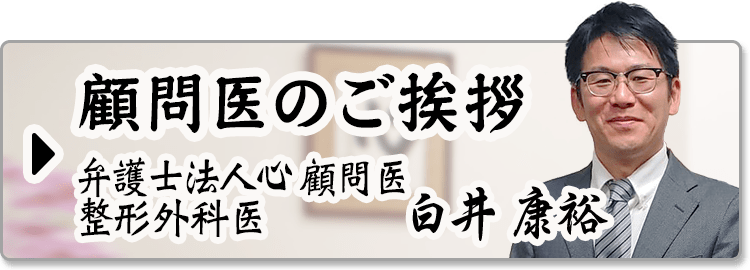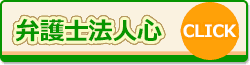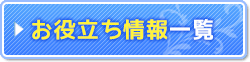「その他の高次脳機能障害情報」に関するお役立ち情報
高次脳機能障害の可能性がある場合の対応
1 事故の直後から経時的な画像所見を得る
自賠責保険により高次脳機能障害と認定されるためには、交通事故(外傷)が原因で脳が受傷したことを裏付ける画像検査結果が求められます。
CTは、頭部外傷時、脳の器質的損傷の有無を確認するために有用です。
MRIは、微細な脳損傷を検出するために有用です。
特に、T2*やSWIは、時間が経過しても微細な出血痕を捉えることが可能といわれています。
また、脳実質(大脳、小脳、脳幹等の脳そのもの)に損傷が確認できなくても、脳萎縮の所見が得られる場合、高次脳機能障害の存在を裏付ける事情となります。
そのため、急性期から慢性期にかけて経時的に脳萎縮を含む画像上の異常所見の有無を把握しておくことも重要です。
特に、局在性脳損傷(脳挫傷、頭蓋内血腫等)と異なり、びまん性脳損傷の場合は、外傷直後のCTでは正常にみえても、MRIでは脳内に点状出血等の所見がみられることが多く、時間が経過すると脳萎縮が目立ち、3か月程度で固定するものと考えられています。
2 意識障害の有無と程度を測定する
意識障害は、脳の機能的障害が生じていることを示す指標とされ、意識障害が重度で長く続くほど、高次脳機能障害が生じる可能性が高くなります。
意識障害の有無や程度は、JCS(ジャパン・コーマ・スケール)やGCS(グラスゴー・コーマ・スケール)という基準で評価されます。
高次脳機能障害の後遺障害を申請する際、医師が作成する「頭部外傷後の意識障害についての所見」を提出する必要があります。
そこで、意識障害の有無や程度を評価した医療記録があるか確認しておくとよいでしょう。
3 症状を漏れなく医師に報告する
高次脳機能障害になると、認知障害、行動障害、人格的変化等の症状が残存し、就労が制限されますが、これらの症状が現れていても、被害者本人は認識することができず、周囲から理解されにくいため、見落とされやすいという特徴があります。
そこで、家族や介護者は、被害者をよく観察し、事故前と比べて少しでも「おかしい」「気になる」「変わった」と思えることがあれば、その都度、メモをとり、脳神経外科の医師に、それらの症状を漏れなく医師に報告することが重要です。
高次脳機能障害における画像所見の重要性 お役立ち情報トップへ戻る